プロフィール

秀吉の甥で関白職を授かる。幼名・孫七郎。古書収集家。
小牧・長久手の戦いでは、八〇〇〇人を率いて、織田信雄・徳川家康連合軍に挑む。しかし池田恒興・森長可は戦死してしまい、秀吉から叱責を受ける。
戦後は改易された信雄の旧領を与えられて尾張(愛知県)清州城に入り、山内一豊・堀尾吉晴・中村一氏らを付与され秀次東海軍団がここに誕生。
秀吉の子・鶴松の夭逝により、秀吉から関白職を譲られて聚楽第に入る。文禄の役では秀次軍団の根拠地が東海のため渡海を免れた一方、秀頼が誕生する――!
詳細
1.小牧・長久手の戦い
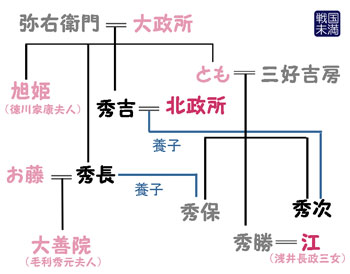
![]() 秀次は、
秀次は、![]() 豊臣秀吉の近臣・三好吉房と秀吉の姉ともの間に生まれた子で、秀吉の甥にあたります。
豊臣秀吉の近臣・三好吉房と秀吉の姉ともの間に生まれた子で、秀吉の甥にあたります。
秀吉は天下統一の過程で、山崎の戦いで![]() 明智光秀を、賤ヶ岳で
明智光秀を、賤ヶ岳で![]() 柴田勝家を討ちましたが、織田家の生き残りである
柴田勝家を討ちましたが、織田家の生き残りである![]() 信長の次男・
信長の次男・![]() 信雄(のぶかつ)と争うようになりました。
信雄(のぶかつ)と争うようになりました。
信雄は、![]() 徳川家康を味方につけて秀吉と断交。天正一二年(1584)秀次一七歳の時に、小牧・長久手の戦い(秀吉VS家康・信雄連合軍)が起こりました。
徳川家康を味方につけて秀吉と断交。天正一二年(1584)秀次一七歳の時に、小牧・長久手の戦い(秀吉VS家康・信雄連合軍)が起こりました。
秀吉軍長久手隊として先手・池田恒興隊、二番・![]() 森長可隊、三番・堀秀政隊、四番・秀次隊で合計二万の大部隊のが組織されると、長久手隊は隠密行動で三河に向かいました。
森長可隊、三番・堀秀政隊、四番・秀次隊で合計二万の大部隊のが組織されると、長久手隊は隠密行動で三河に向かいました。
しかし途中でこの情報が漏れて伝わってしまい、家康対撃隊である先鋒の![]() 榊原康政は、秀吉軍最後尾の秀次軍を攻撃。ふいをつかれた秀次軍は、敵の二倍の兵力を持ちながらあっけなく敗走。家康隊と対峙した池田恒興と森長可、両部隊長は戦死。
榊原康政は、秀吉軍最後尾の秀次軍を攻撃。ふいをつかれた秀次軍は、敵の二倍の兵力を持ちながらあっけなく敗走。家康隊と対峙した池田恒興と森長可、両部隊長は戦死。
八〇〇〇人を率いて出陣した秀次ですが、この顛末(てんまつ)に秀吉から「無分別」と叱責されました。
2.東海軍団長
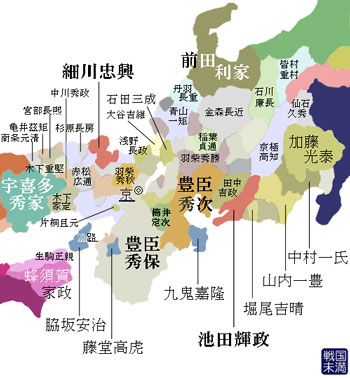
翌天正一三年(1585)七月、秀吉が関白・従一位に任ぜられると、同年閏八月に秀次は紀伊,四国平定(VS![]() 長宗我部元親)の功により、秀吉から近江四三万石を与えられて八幡山を居城としました。
長宗我部元親)の功により、秀吉から近江四三万石を与えられて八幡山を居城としました。
また宿老として、![]() 山内一豊・堀尾吉晴 ・中村一氏・田中吉政らを付与しました。
山内一豊・堀尾吉晴 ・中村一氏・田中吉政らを付与しました。
翌年、秀吉は太政大臣に昇進し豊臣姓を授かり、また京都の居城として聚楽第(じゅらくだい)の造営に着手。天正一七年には、秀吉と![]() 淀殿の間に鶴松が誕生しました。同一八年、秀次は改易された信雄の旧領尾張と北伊勢五郡を与えられ清州城に入り、宿老たちは三河・遠江・駿河で知行を得ました。
淀殿の間に鶴松が誕生しました。同一八年、秀次は改易された信雄の旧領尾張と北伊勢五郡を与えられ清州城に入り、宿老たちは三河・遠江・駿河で知行を得ました。
同年七月の小田原合戦(VS![]() 北条氏政・氏直)には先陣を承り、山中城・韮山城を攻略。翌一九年(1591)、奥州平定(VS九戸政実)のため家康と共に派遣され、検地や刀狩りを実施しました。
北条氏政・氏直)には先陣を承り、山中城・韮山城を攻略。翌一九年(1591)、奥州平定(VS九戸政実)のため家康と共に派遣され、検地や刀狩りを実施しました。
3.関白と太閤の違い
同年八月、鶴松(秀吉の子)の夭逝により同年一二月、秀吉から秀次二四歳は関白職を譲られて聚楽第(じゅらくだい)に入りました。
秀吉自身は太閤と称すも、これは単なる称号にすぎないので勿論、関白に絶対的な権力があります。則ち太閤朱印も、関白の同意がなければ法律的に実行力を持ちませんでした。
その例として、![]() 蒲生氏郷死去後、子息・鶴千代の会津領の相続は、文禄四年二月九日付太閤朱印状、翌十日、関白朱印をもって命ぜられました。大名の昇官叙任、知行宛行についても指示するのは太閤でしたが、給知権を有するのは関白でした。
蒲生氏郷死去後、子息・鶴千代の会津領の相続は、文禄四年二月九日付太閤朱印状、翌十日、関白朱印をもって命ぜられました。大名の昇官叙任、知行宛行についても指示するのは太閤でしたが、給知権を有するのは関白でした。
文禄元年(1592)四月、秀吉の明国制圧の野望により日本軍が朝鮮に侵攻すると、秀次は国内にあって継舟・次飛脚の制度を定め、兵糧米の確保や独自の軍事編成によって京畿の警護にあたりました。
翌年八月、秀吉と淀殿の間に![]() お拾い(秀頼)が誕生すると、秀吉との間に亀裂が入りました。
お拾い(秀頼)が誕生すると、秀吉との間に亀裂が入りました。
関白としての秀次は、天皇の意思を取り次ぐ立場にあり、公家・寺社・官位・交通など国家的事象に関わる事柄でした。他方で秀次は、尾張を中心とする独自の家臣団を有していましたが、秀吉は尾張に検地を派遣して、政治的監察を行い尾張の実態を掌握しました。
4.秀次事件
同四年(1595)七月、秀吉は秀次に謀反の疑いをかけて出家させ、無位無官としたうえで高野山に追いやり、秀次は一五日に切腹させられました。享年二八。
八月二日、子女・妻妾ら三〇余人も京都三条河原で処刑され、多数の近臣も殺されました。この妾の中には最上義光の娘が含まれ、![]() 細川忠興は秀次に借金、果ては
細川忠興は秀次に借金、果ては![]() 浅野幸長や
浅野幸長や![]() 伊達政宗らも嫌疑をかけられました。これら部将の共通点は反
伊達政宗らも嫌疑をかけられました。これら部将の共通点は反![]() 石田派。
石田派。
もとより宿老の山内一豊らはじめ東海軍団はどうなってしまうのか、全国各地の大名に波紋を広げました。ちなみに![]() 浅野長政側の政宗はこれを機に、長政に絶交を申し渡すに至りました。
浅野長政側の政宗はこれを機に、長政に絶交を申し渡すに至りました。
一方で七月の秀次事件より三ヶ月前には、秀次の弟である大和郡山城主・秀保一七歳が謎の死を遂げています。また同事件の一年後の慶長元年(1596)閏七月に畿内大地震、一一月には秀吉によりキリスト教信者二六人が処刑、翌二年に日本軍は朝鮮へ再出兵となりました。
5.古筆家(こひつけ)の誕生
書画の目利きを業とする家が、豊臣時代に至って起こりました。則ち古筆(こひつ)という家です。
その祖は近江の了左櫟材(りょうさ-れきざい)が、連歌・茶道・書道に秀で、筆蹟の鑑定に巧みであったために、関白・近衛前久の信任を得、その勧めによって古筆鑑定を業とするに至りました。
たまたま秀次は古筆を好み、了左に古筆の苗字と「琴山」(きんざん)の印とを与えて公認。古筆了左の子・一村および了栄に至り両家に分かれましたが、その後両家ともに江戸幕府の古筆見の役を申付けられ、明治期まで古筆鑑定の専業の家でした。一方の秀次は古書を収集、経典の補修などにも意を払いました。
書道セット 大人 習字 写経 筆 文鎮_Amazon
豊臣秀次 相関図
豊臣氏
同氏政権
秀次付 宿老
小牧・長久手の戦い
参考文献
- 三鬼清一郎『鉄砲とその時代(読みなおす日本史)』(吉川弘文館 、2012年)
- 三鬼清一郎「豊臣秀次」『国史大辞典10』(吉川弘文館、1989年)458頁
- 黒田和子『浅野長政とその時代』(校倉書房、2000年)「第十四章 関白賜死」335頁
- 伊木壽一『日本古文書学』(雄山閣出版、第三版1990年)「第一章 序説」27頁
- 奈良本辰也 監修『戦国武将ものしり事典』(主婦と生活社、2000年)「小牧・長久手の戦い」138-143頁