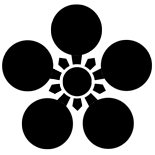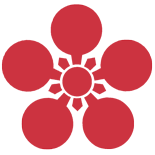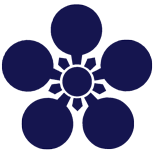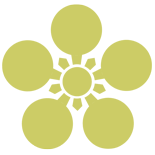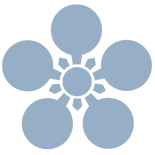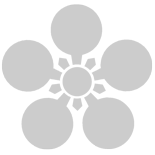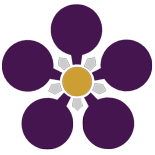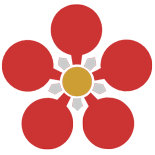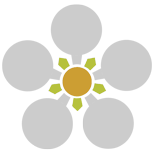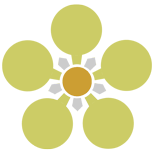家紋の由来
天神信仰と梅
林羅山曰く「菅神(かんじん:菅原道真)は梅を愛し、梅は花の中の儒なり」『菅神賛』
菅原道真を祀る、京都の北野天満宮の神文は梅鉢で、東京都江東区の亀戸天神社は変わり剣梅鉢です。
天正一五年(1587)一〇月一日、北野天満宮社頭の松原における秀吉主催の大茶湯。秀吉が北野松原を選定した理由は、彼の天神信仰(てんじん しんこう:菅原道真の霊を祀る)と恰好の場所であったと推測されます。
この北野大茶湯において秀吉は自ら、公卿、一族、武将に茶を点じてました。その中には一番に、家康・織田信雄ら、二番には豊臣秀長・秀次、![]() 前田利家らが居ました。
前田利家らが居ました。
家紋として
梅紋の分布は、天神信仰の盛行した地方に当ります。具体的には、菅原の出自と称する者もが多い大和と近江、次いで美濃、越前、加賀、美作など。
梅鉢と梅花と違いは、梅鉢はイラストのように真ん中の丸い芯の周りに「鉢」(ばち)なる装飾が施されています。鉢は太鼓のたたく棒にも見え、梅花と区別する為に梅鉢と言われるようになりました。
利家と利長の紋は、別名・剣梅鉢(けんうめばち)ともいわれ、鉢が特に長く、花弁の間に出ているものは剣梅鉢と呼ばれています[補註]。
前田氏:金沢藩
補註
徳川の時代になると、前田家臣の中ではこの梅鉢紋を暗号のように使っていたという。「徳川氏にいつか…」とその機を狙う武功派は剣梅鉢の剣を長くし、学問・文化を通して仲良くという文治派は、梅鉢の剣を短くという印(しるし)に使っていたといわれる。
参考文献
- 竹内秀雄『天満宮』(吉川弘文館 新装版、1996年)「一 天神の象徴 2菅神と梅」4-8頁「七 北野社と芸能 1北野大茶湯」185-198頁
ご利用について
フリー素材のご利用規約をご参照ください。