プロフィール

織田家老臣の一人。尾張(愛知県西部)山崎城主。幼名は牛助。
殿軍(でんぐん)の指揮を得意とし、「退(の)き佐久間」の異名をもつ。
武田信玄VS徳川家康の三方ヶ原の戦いで、家康の要請により織田軍の援軍として参戦したが大敗。
武田勝頼VS信長の長篠の戦いでは、先鋒隊をつとめ因縁の武田軍を打ち破る。
詳細
1.佐久間一族
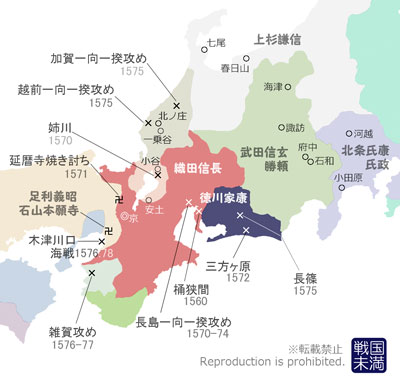
尾張(愛知県西部)に生まれた信盛は、佐久間信晴(のぶはる)の長男。
佐久間氏は桓武平氏。三浦義村の三男家村を祖とします。家村が安房(あわ)平群(へぐり)郡佐久間郷(千葉県安房鋸南町)に拠り、そののち尾張に移ったとされますが、詳細ははっきりしません。
祖父の盛通(もりみち)のころより織田氏に仕えていたようで、その孫の盛次(もりつぐ)と信盛はともに![]() 信長の重臣となりました[相関図]。盛次の妻は
信長の重臣となりました[相関図]。盛次の妻は![]() 柴田勝家の姉で、子の盛政ははじめ信長、のちに母の弟・勝家に仕えました。
柴田勝家の姉で、子の盛政ははじめ信長、のちに母の弟・勝家に仕えました。
信盛ははじめ織田信秀(信長の父)に仕え、のちに七歳下?の信長に従い、永禄三年(1560)信盛(三四歳?)は![]() 桶狭間の戦いに従軍。
桶狭間の戦いに従軍。
同一一年(1568)信盛(四一歳?)は信長の上洛に従い、京都近辺の政務に関与するとともに各地を転戦。元亀元年(1570)![]() 姉川の戦いにも従軍しました。
姉川の戦いにも従軍しました。
2.三方ヶ原の戦い
![]() 足利義昭は将軍就任後、支援者であった信長と次第に対立。
足利義昭は将軍就任後、支援者であった信長と次第に対立。![]() 武田信玄を味方につけて、元亀三年(1572)信長の同盟軍である
武田信玄を味方につけて、元亀三年(1572)信長の同盟軍である![]() 徳川家康を(静岡県)三方ヶ原にて攻撃させました。
徳川家康を(静岡県)三方ヶ原にて攻撃させました。
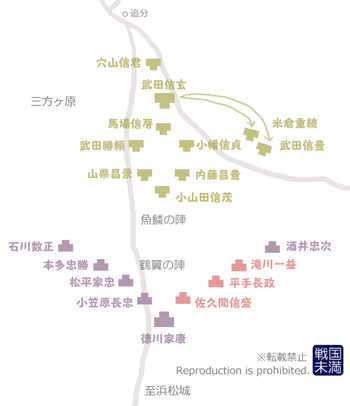
信長は本願寺顕如・![]() 朝倉義景・浅井長政の包囲陣を敷かれていて動けなかったため、信盛(四五歳?)・滝川一益四八歳・平手長政(二〇歳?)ら三〇〇〇の兵を三方ヶ原の戦いに送りました。
朝倉義景・浅井長政の包囲陣を敷かれていて動けなかったため、信盛(四五歳?)・滝川一益四八歳・平手長政(二〇歳?)ら三〇〇〇の兵を三方ヶ原の戦いに送りました。
武田軍二万五〇〇〇に対し、徳川軍は援軍合わせても一万一〇〇〇。しかも信玄はいくさ上手。家康は鶴翼(かくよく)の陣を敷いて、右翼に![]() 酒井忠次・一益・平手長政・信盛、中央に家康本隊、左翼に
酒井忠次・一益・平手長政・信盛、中央に家康本隊、左翼に![]() 本多忠勝・石川数正らを配し、総力を集めて攻撃。しかし平手長政は戦死し、徳川・織田軍の大敗に終わりました。
本多忠勝・石川数正らを配し、総力を集めて攻撃。しかし平手長政は戦死し、徳川・織田軍の大敗に終わりました。
天正二年(1574)、信長が勅許を得て東大寺秘蔵の蘭奢待(らんじゃたい:中国から伝来した香木)を切り取った際には、奉行を務めました。
また、信長が伊勢長島の一向一揆を攻めた時は、柴田勝家らと攻め入り、これを鎮圧しました。
3.長篠の戦い
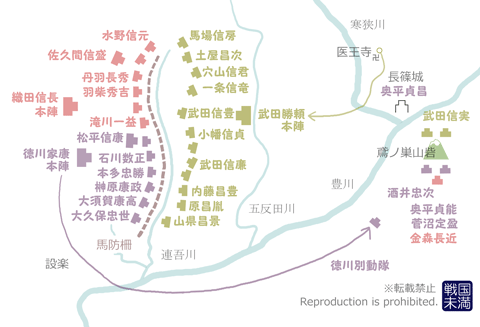
同三年(1575)長篠の戦い前夜。信玄以来の老臣たちは、![]() 武田勝頼にこの度の戦いは中止するよう諫めました。しかし勝頼側近の長坂長閑(ちょうかん)と跡部勝資(かつすけ)たちが出兵を主張して譲りません。
武田勝頼にこの度の戦いは中止するよう諫めました。しかし勝頼側近の長坂長閑(ちょうかん)と跡部勝資(かつすけ)たちが出兵を主張して譲りません。
それは信盛から、信長には恨みがあるので勝頼公に仕えたい、合戦のときには必ず信長に裏切りを働く、という申し入れがあったからでした。この偽りに際し信盛は予め信長に、信長の佩刀(はいとう)と起請文を添えれば信用するだろうと話し、信長は大刀では人目につくから脇差がよいだろうとしました。
それが全ての要因とは限りませんが、勝頼は野戦に誘い出され、武田軍と織田・徳川連合軍が設楽ヶ原(したらがはら)に退陣。信盛(四八歳?)は織田方の先鋒隊をつとめ、滝川一益とともに鉄砲隊を指揮して、因縁の武田軍を打ち破りました。(長篠の戦い)
4.石山本願寺攻め
同四年(1576)以降、本願寺顕如との石山合戦において、近江・尾張など7か国の軍勢を指揮しましたが、荒木村重の反乱などで長期化しました。
同八年(1580)信盛(五四歳?)の時に石山開城となるも、その一〇日後、突然信長からその怠慢を責めた譴責(けんせき)状を突き付けられ、信盛は子の信栄とともに高野山へ追放されました。その一年後、紀伊国十津川の温泉で病気療養中に病死しました。享年五五?
5.譴責状の内容
『信長公記』には、信長が信盛に突き付けた譴責(けんせき)状の内容が記載されているのでご紹介します。
- 一、父子(信盛・信栄)共に五か年天王寺に在城している間(石山合戦)、よい武勲(ぶくん)が一つもなかった。
- 一、先年(天正元年)朝倉勢を討ち取った時、勝機をのがしたことをけしからぬと申した所、恐縮するどころか自分の正当性を吹聴し、座敷をけって出た。これによって信長は面目を失った。
- 一、信栄の心ばえのよくないことは、一つ一つ数えあげても書ききれないほどである。
- 一、第一に欲が深い。その上いいかげんに物事を処理し、とどのつまり父子ともに武士の道に欠けているからこのような事になった。
- 一、やさしいふりをして、実際には錦の中に針を隠し立て、家臣に恐ろしい扱いをしたのでこのような事になった。
- 一、信長の代になって三十年も奉公している間に、比類のない働きをしたと称されるようなことは一度もなかった。
他人にここまで言う人、言われる人もなかなかいまい。
AIボイスレコーダー 112ヶ国語対応_Amazon
佐久間信盛 相関図
佐久間氏
信盛系
- 祖父:盛通(もりみち)
- 父:信晴(のぶはる)
- 弟:信辰(のぶとき)。享年六二
- 子:正勝(信栄、不干斎:ふかんさい)。享年七六
盛次系
- 伯父:盛重。盛通の子。
- いとこ:盛次。盛重の子。妻は柴田勝家の姉。
- 盛政:盛次の長男。賤ヶ岳の戦いで敗死。享年三〇
- 勝政:盛次の三男。勝家の養子。享年二七
織田政権
ライバル
参考文献
- 小和田哲男「佐久間氏」左同(監修)左同・菅原正子・仁藤敦史(編集委員)『日本史諸家系図人名辞典』(講談社、2003年)323-324頁
- 柴辻俊六「佐久間信盛」『国史大辞典6』(吉川弘文館、1985年)317-318頁
- 会田雄次『戦国百人一話1 織田信長をめぐる群像』(青人社、1991年)
- 小和田哲男 監修『ビジュアル 戦国1000人』(世界文化社、2009年)
- 奈良本辰也 監修 『戦国武将ものしり事典』(主婦と生活社、2000年)「長篠の戦い」106-113頁