フリーイラスト PNG形式/背景透過
商人
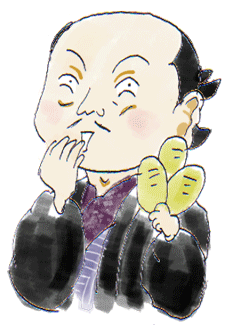
解説:商人の服装
江戸時代の商家は、主人を頂点とし、奉公人である番頭頭(がしら)・番頭・手代・丁稚が続きます。服装もそれぞれ定められていました。
商家の商人は、縞柄の小袖(こそで)を平絎帯(ひらくけおび:平たく仕立てた幅の狭い男性ものの帯)などで結び、その上から羽織を着用。羽織は店主の特権でした。また通常、商家の人々は袴をはかない着流し姿。足には季節に足袋を履き、外出時は草履、雪駄(せった)を履きました。
以上、池上良太『図解 日本の装束 (F-Files No.018) 』(新紀元社 、2008年)106-107頁。
定めなのだろうか。というのも、荻生徂徠『政談』に曰く「御役人・奉行などの無礼甚だしくなり、下たる者は礼に過ぎて這(は)い屈(かが)み、諂(へつら)う風俗甚だしきは、制度無きを以ってである。」
これに対し朝鮮王朝は官吏の服装に見られるように、制度によって細かく規定されています。
日本では多々ある儒教徳目の中で忠が極端に発達。当時戦争もなく、武家より商家の方が勢いがあった分、服装についても商家の方がやかましかった可能性は無きにしも非ずのような気もします。