用例
"動かざること山の如し"、テレビの前に、しっかりと、あるいはどっしりと陣取っているナンシー関である。『ナンシー関―トリビュート特集』から川村邦光(民俗学・宗教学)
孫子とは
知っているようで、知らない![]() 武田信玄が掲げる「風林火山」。その出典は、古代中国古典『孫子』です。諸子百家の一派・兵家の書で最も優れた書が『孫子』一三篇と言われています。風林火山の記述は第七軍争篇にあり、前文(要約)→風林火山→直後の文章を以下に見ていきましょう。
武田信玄が掲げる「風林火山」。その出典は、古代中国古典『孫子』です。諸子百家の一派・兵家の書で最も優れた書が『孫子』一三篇と言われています。風林火山の記述は第七軍争篇にあり、前文(要約)→風林火山→直後の文章を以下に見ていきましょう。
第七 軍争篇
前文(要約)
用兵(戦いで兵を動かす)の法では、軍争(機先を制すること)ほど難しいものはない。
軍争は難しいが廻り道をとって、ゆっくりしているように見せかけて、敵を誘導しながら出て敵よりも先に戦地に行き着く。これが迂直(うちょく)の計(廻り道を近道に転ずるはかりごと)を知る者である。
また、山林の様子や土地の険しさ易しさ、沼沢の有無などがわからなければ軍を進めることができない。
戦いは、敵をあざむくを根本とし、敵の状況に応じて兵を分離させたり、合わせたりして対応せよ。
風林火山

速きこと風の如く、徐(しず)かなること林の如く、侵略すること火の如く、動かざること山の如く
(意訳:攻めるべき時には風のようにすみやかに襲いかかれ。準備を整え、機会の来るのを林のように静寂整然と待て。いざ侵攻するときは、火のように熾烈に戦え。一度動くまいと決心したら、敵に挑発され攻め立てられても、山のように落ち着いて自陣を堅守すべし。)
続き
村落で物資を掠(かす)めとるときは衆を分け、土地を奪うときは仕事を分け、臨機応変に動く。迂直の計を知る者が勝つ、これが軍争の法である。
おまけ
2007年 JR東日本・風林火山号のツアー
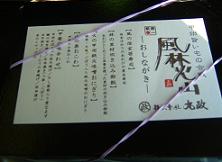


お弁当の箱および家紋❖(割菱:わりびし)に区切られた中身/記念品
風林火山の前文から後ろまで見てきましたが、まさかの泥棒の教え?!戦争というのは文禄・慶長の役しかり、つまりこういうことなのだと、ある意味リアルによくわかりますね。
さて、2007年大河ドラマ・風林火山にちなんだJR東日本の風林火山ツアーに「お金を払って」行って来ました(笑)。JR東日本長野支店よりもらった記念品は、ハサミ・ルーペ・定規・などが備わった多機能な文房具。事前に知らされてないだけあって、驚きうれしかったです♪
参考文献
村山吉廣 訳「孫子」『中国古典文学大系 4』(平凡社、1973年)434-435頁